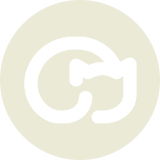一直以来,许多幼教工作者和家长都将儿童的攻击性行为看做不良行为、行为问题,当遇到儿童的攻击性行为时,都尽力地去制止以及帮助儿童改正。幼儿不同的攻击性行为有不同的原因,而老师和家长了解幼儿的攻击性行为,了解它产生的原因,并针对他们的攻击性行为采取有效的措施,这是从古至今教育专家一直在进行深入研究的一个问题。
一些常见的攻击性行为发生频率较高的年龄阶段一般处于儿童期和青少年期。家庭是儿童基本的生活场所,也是儿童的第一社会场所,儿童早期的攻击性行为与家庭有着密不可分的关系。父母是孩子人生中的第一任老师,来自父母的教育影响着孩子的成长。因此,要减少幼儿的攻击性行为,我们不仅要从幼儿的家庭因素出发,还要进一步地了解幼儿的性格特征,了解孩子产生攻击性行为的原因用恰当的方法来帮助孩子减少攻击性行为。
我国学前教育专家就幼儿攻击性行为这一问题进行着长期而深入的研究,颇有成效。他们站在不同的角度去观察,发现,并进行分析和研究,将幼儿产生攻击性行为的原因与家庭教育,幼儿园教育紧密结合,取得了一定的成绩。本研究将重点放在调查幼儿攻击性行为的表现特征,产生原因以及如何解决这三点上面,去发现实践过程中存在的问题,针对以往的研究不足提出相关的看法和建议。
(二)研究目的
通过实际的调查了解幼儿攻击性行为的真实现状,并结合国内外对幼儿攻击性行为已有的研究,分析幼儿攻击性行为的原因以及影响幼儿攻击性行为的诸多因素,更有效地帮助幼儿改正不良行为,促进幼儿良好行为的产生及形成良好习惯。与此同时,就幼儿社会认知发展这一问题也提出一定的建议。
(三)研究意义
对幼儿来说,纠正其攻击性行为,有利于推动其良好行为的产生以及有助于幼儿形成正确的社会认知,帮助幼儿更好的融入集体,从而推动其社会交往技能以及社会交流能力的发展,便于以后更好的进入社会大环境。对于幼儿教师来说,教师可以更深入地了解幼儿的攻击性行为以及各种针对此问题的有效的解决方法和技巧,教师得以更好地处理孩子的攻击事件。而幼儿攻击性行为的频率降低后,老师也能更有效、更容易地处理好班级中的各种关系。凝聚班级力量,便于教师更好的完成教育目标,培育全面发展的幼儿。对家长而言,有助于帮助家长找到自身家庭教育的缺陷,找到正确应对幼儿攻击性行为现状的合理可行处理方法,从而纠正幼儿的攻击性行为甚至其它不良行为。 对幼儿园而言,有利于幼儿园更好地管理幼儿的行为习惯,更直接地帮助幼儿纠正其不良行为习惯,可降低幼儿攻击事件发生的频率,在一定程度上,可避免幼儿园中一些意外事故的发生,保证幼儿园的安全管理的有效性。
(一)研究对象
本研究随机选取成都市的五所幼儿园为研究对象。
本次的家长调查问卷一共发放114份,回收问卷112份,有效问卷105份。
本次访谈是在五所幼儿园内随机选取了20位任课老师进行了面对面的采访交流。
除此之外,我们还对35名出现过攻击性行为的幼儿进行了仔细的观察记录。
(二)研究方法
文献法,通过搜集和分析关于幼儿攻击性行为现状的研究资料,从中提取有效信息,从而了解到儿童攻击性行为的产生原因、该行为的发展以及对症治疗方法。
访谈法,随机选取在职的幼儿教师进行面对面的采访交流,以此来了解教师对幼儿攻击性行为的专业认识、处理方法,以及专业的建议。
观察法,研究者在明确研究目的和提纲,准备好观察记录表的情况下,对出现了攻击性行为的幼儿进行直接的观察,以此了解攻击性行为幼儿的表现,更好地采取有力措施来帮助幼儿改正不良行为。
问卷调查法,通过随机向所抽查幼儿园的家长发放问卷调查表,收集整理后,了解该幼儿园幼儿攻击性行为的现状等。
统计分析法:对所调查问卷进行统计分析并最终形成数据,分析具有攻击性行为幼儿的情况、表现特点,以及家长和老师对此行为的观点、做法等。
(三)数据统计与处理
采用“问卷星”软件对调查得到的数据进行统计分析
调查结果表明家长开始关注孩子的攻击性行为,意识到该行为问题的严重性,部分家长对幼儿的攻击性行为有一定的了解,并且能关注孩子为什么会这样做,进而采取措施帮助孩子。
经过调查报告显示,只有少部分的家长对幼儿的攻击性行为比较了解,近87.72%的家长对幼儿的攻击性行为略知一二。当幼儿发生攻击性行为的时候,63.16%的家长认为应该及时制止,并且有65.79%的家长会引导幼儿自己解决与同伴发生的冲突。但是仍然有部分家长对幼儿的攻击性行为并不了解,并且有着错误的理解,不重视幼儿产生的攻击性行为,在幼儿周围造成了一些负面的影响。从家长从对幼儿攻击性行为的原因看法及处理办法来看,许多家长还停留在不理解、看表面甚至随意贴标签的层面上,处理引导的方式方法也不够恰当。有的家长还认为在教育孩子处理孩子行为问题上老师是占主要责任,认为家长能起到作用不大,甚至消极地期望老师全权解决孩子问题。所以家长在看待幼儿的攻击性行为中还存在以下问题:
(1)家长不正确的态度观念
在调查的所有家长当中,超过60%的家长认为幼儿在出现攻击性行为是应该马上制止,但是还是有36.84%的家长认为幼儿出现攻击性行为是因为幼儿小,只要哄哄孩子或者任由孩子闹一会儿就好,家长有时会忽略幼儿发生的攻击性行为,导致孩子与同伴发生冲突矛盾,4.39%的家长会选择不管不问。
(2)家长不恰当的处理方式
不同职业、学历的家长对幼儿的攻击性行为也有着不同的看法和做法,有些家长还持着老旧而且错误的教育观教育孩子。从以上问卷结果可以看出有57.89%的家长教育孩子是通过打骂的方式,甚至有43.86%的家长会在孩子面前与其他人发生冲突。家长如果经常打骂孩子,不尊重理解孩子,这样下去,不仅对纠正孩子攻击性行为没有帮助,还会适得其反。
(3)家长对孩子的教育不积极,不主动
问卷的开放性问题结果表明许多家长认为老师担负着教育孩子的主要职责,忽视了家长在孩子成长发展中的重要影响,对孩子在生活中的不良行为习惯甚至是攻击性行为不闻不问,所以孩子在成长的过程中失去了许多该有的引导。
(4)家长很少陪伴孩子,不了解孩子
调查结果显示在被调查家庭中将近50%的孩子是由除父母以外的亲人抚养,父母因为工作等原因难免忽略孩子。家长不够了解孩子的身心发展特点,缺乏对孩子的陪伴以及心理健康及社会性发展的关注。除此之外家长与老师也缺乏沟通,没有为孩子创设家园一致的良好氛围。
(5)家长忽视孩子的观察模仿能力
调查结果显示有43.86%的家长会在孩子面前与其他人发生冲突,另外有31.85%的家长反映孩子模仿过电视节目中的暴力行为。孩子的主要学习方式之一便是观察模仿,但这时候他们的是非辨别能力还很弱,需要家长为他们起到良好的示范、筛选他们接触的环境与刺激物,这样才能有效地预防孩子模仿错误行为养成不良习惯,而许多家长在这方面是很忽视的。
(二)访谈现状及原因分析
1.教师的访谈
在我们所访谈的二十位教师中,每位教师对幼儿的攻击性行为都有自己的理解和教育观点,在幼儿教育实践中,针对幼儿出现的攻击性行为会巧妙地处理引导。通过访谈,我们了解到老师们十分关注幼儿攻击性行为,并相信孩子这样做一定有着他的特殊原因,找到原因才能“对症下药”。不同的孩子性格特征不同,所以我们在采取措施的前提下要总结出不同的解决方法,但是怎样更好地帮助孩子纠正其攻击性行为问题存在很多问题,如下:
(1)老师和家长对幼儿的观察和理解存在不足
不同年龄阶段的孩子,其身心发展特点是有所不同的,他们所出现的攻击性行为就不能一概而论,如年龄较小的幼儿常常因为不懂得如何表达自己如何与同伴交往而出现攻击性行为【1】,在访谈中了解到许多家长老师常常会给孩子冠上“调皮”“不讲道理”“坏孩子”之名。这样不仅不能够消除孩子的不良行为,更容易影响孩子的身心,适得其反。另外,孩子出现攻击性行为是有各种各样的原因的,如情绪不好、产生矛盾、争抢玩具、愿望没有得到满足、受到误解委屈、模仿等,然而日常生活中教师和家长对幼儿了解与观察都不足,通常在没有把问题了解透彻的时候就开始尝试解决,同时在孩子出现行为问题的时候不够耐心,也没有给他足够的空间去成长改正,家长和教师的这一问题将直接造成孩子真正的意愿被忽视、曲解甚至被引导向一个错误的方向。
(2)幼儿园为幼儿开设的心理健康教育不够
在访谈中了解到,老师更多地只是在幼儿出现攻击性行为时去着手调解和引导,在幼儿园的课程活动开展中较少有关幼儿心理健康的内容,所开展的幼儿心理健康活动也显得形式、空洞和泛化,缺乏针对性,并没有结合幼儿实际来设计开展【2】。由此看出,幼儿园及幼儿老师对幼儿心理健康的不同程度的忽视也可间接或者直接导致孩子频发攻击性行为。
(3)教师与家长给孩子的引导及保护不到位
孩子最初的学习方式中最重要的观察模仿学习,他会从他所接触的环境以及各种刺激物中汲取养分获得经验以发展。但是由于孩子年龄的因素这个时期的小朋友辨别能力不高,尤其需要家长和教师在日常生活中的引导和保护,在访谈的过程中我们意识到,随着社会的进步和科学的发展,我们的孩子们能够接触到的东西越来越多也越来越杂,很明显的能看到有的孩子就受动画片里某些暴力片段的影响,在现实中模仿该片段而出现攻击性行为。老师和家长并没有起到良好地保护和引导作用,不重视对孩子接触的环境和刺激物的筛选,没有让孩子明确什么行为是错的是坚决不能够做的【3】。另外一方面老师和家长在孩子面前不注重自己的行为规范也容易导致孩子错误模仿。
(4)家园合作不够完善
在与老师的交流中我们发现如果有孩子对其他小朋友做出攻击性行为,虽然老师当时会快速的处理好问题,但是事后却几乎没有和孩子家长沟通交流小孩的问题。孩子的成长需要得到家长和老师的共同引导和爱护,如果单靠其中一方解决不了根源问题。即使幼儿没有出现不好的行为,但是为了等进一步的家园合作和更加全面了解幼儿的情况,教师与家长之间就要建立良好的沟通桥梁,当孩子出现不良行为问题及其他各问题时,可以帮助老师和家长更及时更准确地寻找原因分析原因,才能更有效地帮助孩子解决问题、改掉不好的行为习惯。【4】