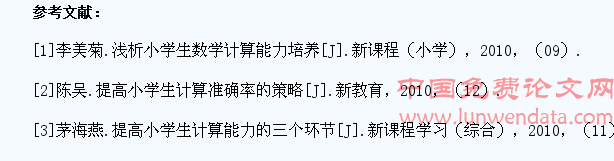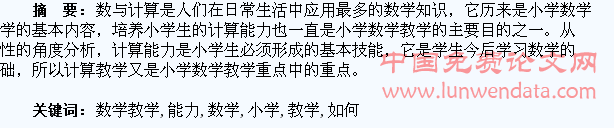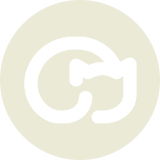一、小学数学计算教学存在的主要问题
1.学生缺少学习的积极性
对于小学生来说,数学是抽象、难懂的,是枯燥乏味的。而传统的计算教学,“纯粹的计算”又成了核心的内容,与实践应用严重的脱节,使得计算课更加显得无趣、枯燥、单调。因此让很多的学生“望算生畏”,继而导致“望数生厌”,从此对数学的学习丧失了信心。学生的计算能力下降了,具体表现为计算的正确率下降、口算速度变慢、简便运算方法不够灵活等等;导致学生注意力不集中,上课走神;作业不按时交,抄袭其他同学的数学作业;计算结果正确而计算过程不对的现象时有发生。这些都是学生缺少学习积极性的突出表现。
2.概念不明确,算理不理解
在计算教学中,有些教师认为计算没有什么道理可讲,只要让学生掌握计算方法后,反复“训练”,就可以达到正确、熟练的要求了。结果,不少学生虽然能够依据计算法则进行运算,但因为算理不清、生搬硬套运算法则,知识迁移的范围就极为有限,无法适应计算中千变万化的各种具体情况。传统方法授教,重技能的讲解,轻算理的探究,就会造成学生只知道要这样算,而不知道为什么要这样算,在计算时知识性的差错就会出现。
3.忽视口算练习
口算是计算的基础。但有些教师及学生口算意识淡薄,从而忽视口算的速度以及口算的正确率,在课堂上也很少安排时间 展口算的训练。任何一道整数、分数或小数四则运算都可以分解成一些基本口算题。如果口算不熟,计算时必然会出现错误。只要计算中有一步口算出错,就会导致整道题的计算结果错误。甚至有的一年级学生就连20以内的加减法都不熟练,有的二年级学生连乘法口诀也没能做到脱口而出……,这样的口算水平,势必会影响计算速度和正确率。
4.估算意识薄弱
《数学课程标准》指出要“重视口算,加强估算”在实际课堂教学中,多数教师很难做到这一点。计算教学历来只重视运算技能和技巧的训练,在估算教学中,大部分老师着重训练学生的估算方法,认为只要在学生做估算题的时候,能非常熟练地找到估算的结果,这便完成了估算教学的目标,忽视了估算方法的感悟与估算意识的培养,使估算被动地存在于学生的头脑之中。
二、改进小学数学计算教学的策略
1.激发学生的学习兴趣
“兴趣是最好的老师”。激发学生的计算兴趣,使学生乐于计算,全身心投入计算中并获得成功体验是提高学生计算正确率的首要条件。通过教育心理学的研究表明,学习兴趣是学生学习的动机中最现实、最活跃的成份,只有当学生对它产生了浓厚的兴趣,真正喜爱所要学习的东西时,才能够真正的学好它。学习常常是与一些特定的社会背景相互联系的,想要利于学生的意义建构,只有在真实的情境之中学习才会达到这样的效果。若创设情境,而且通过开展情境去学习,对于计算,学生才是把它当作了一种工具,才能利用自己的所学,通过计算去解决一些实际生活中的各种问题,从而体会计算在现实生活中的价值,以此来激发学生学习的兴趣。
2.注重策略的优化,引导学生领悟算理
学生学习的方法是否科学与正确,直接影响着学生学习效率的高低,因此学习方法比知识更重要。所以在教学过程中,要使学生“学”而且能“会学”。而在小学的数学计算学习中,我们所说的学习方法可以理解成计算的算理。为什么要这样计算?这样的计算方法我们是怎样得到的?追其源,溯其因,学生也就能慢慢的掌握了。准确的计算必须构建在透彻地理解算理的基础上,学生的头脑中只有算理清楚,法则记牢固,在做计算题时,才可以有条不紊地进行。
3.算法的多样化与优化
《数学课程标准》关于计算教学的基本理念之中就包括算法多样化,它的用意是让学生能够利用所学的知识以及经验和方法,通过独立的思考和积极的探索,从而在有效的学习活动中开发创新潜能。“算法多样化”是新课标改革的一个亮点,提倡并鼓励算法多样化,有利于“不同的学生得到不同的发展”,但算法并不是越多越好。教学时我们面对学生各种各样的算法时,要注意分析这些算法的特点、局限性,适时引导学生的思维,对算法进行优化。但优化的过程不是由老师“灌”出来的,而是让学生在解决问题的过程中自主探索,在师生互动,生生互动,体验多种方法的基础上自我感悟。
4.扎实掌握计算知识
(1)运算顺序。运算顺序是指同级运算从左往右依次演算,在没有括号的算式里,如果有加、减,也有乘、除,要先算乘除,后算加减;有括号的要先算小括号里面的,再算中括号里面的。只有掌握了运算的顺序,才是做对计算题的保障,也是提高学生计算能力的重要一环。
(2)计算法则。在学生充分理解及掌握了算理后,教师应适时引导学生对计算的过程进行反思、推敲,并启发学生再思考。法则和算理都是计算的依据。正确的计算必须构建在充分地理解算理的基础上,以及学生的头脑中算理要清楚,法则要记牢,再去做四则计算题时,学生就能有条不紊地进行了。
(3)认真审题,多思善想,准中求活。计算正确、方法合理、灵活的前提就是认真审题。要让学生养成认真校对的习惯,要求学生对于所抄写下来的题目都进行认真校对,细到数字、符号,不错不漏。要让学生养成认真审题的习惯,要求学生看清题目中的每一个数据和运算符号,确定运算顺序,选择合理的运算方法,看看是否可以简算,又怎样简算。
三、结论
计算教学是小学数学教学中的重要内容。有效地分析学生在计算学习中出现的问题,把握影响学生计算准确率或准确性的各种原因,对于提高我们数学教育教学也有着十分重要的影响。纵观目前的计算教学,我们既要继承传统计算教学的扎实有效,又要发扬以人为本的教学理念,更要冷静思考计算教学对学生后续学习能力的培养,不断总结经验教训,不断改善教学方法,使计算教学在算理、算法、技能这三方面得到和谐的发展和提高。